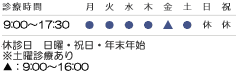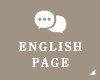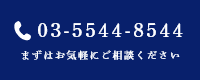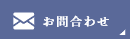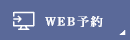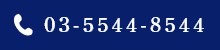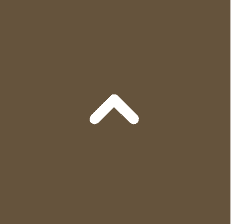むし歯治療において最善の結果を得るには削り方を考えないといけません。

皆さんが良く受けられるむし歯の治療
その結果が良くなるのか、悪くなるのか、それは
どうそのむし歯を削ったかにかかっています。
多くの歯科医は回転する器具で徹底的に削り取ります。
さらにはむし歯部分を染色して、さらに必要のない部分まで取ってしまっているのです。残念ですが、それって歯に悪い可能性が高いのです。ビックリでしょうが、以下に理由が書かれてあります。
東京国際歯科 六本木 院長は根管治療・保存修復分野で30年以上の臨床経験を有し、国内外学会での研究発表や米国歯内療法学会(AAE)等の国際学会への参加実績があります。2007年には世界的な事業であるコクラン共同計画に参加、コクランレビューという世界で最も信頼性の高い情報をまとめるという仕事に携わりました。その際のテーマは、深いむし歯のある歯をどう治療したら、その神経を取らないで維持することができるかで、レビューをマンチェスター大学のクアトロ教授と共同研究を発表しています。長年の臨床で培われた症例選別能力と、歯髄温存を重視した治療判断が、当院のう蝕管理の基盤です。
Expertise(専門性)— 選択的削合 vs 非選択的削合(臨床的整理)
- 定義(簡潔)
- 選択的削合(selective/partial caries removal)
- 歯髄近接部では手用の器具を用い、取れるところまで完全に取ります。辺縁部は回転器具を用い、もっと健全歯質まで削合して高品質に封鎖する方法。歯髄保存を優先する戦略。
- 非選択的削合(non‑selective/complete caries removal)
- 目視・触診で認められる感染象牙質を回転器具を用い可能な限り完全に除去し、健全象牙質まで到達させて修復する従来法。
- 目的の差異
- 選択的:歯髄の不可逆的損傷を回避し、切削量を抑えて歯の長期機能を維持することを重視。残存細菌は密閉により不活化されることを期待。
- 非選択的:即時的な感染源の除去と修復物の長期耐久性確保を優先。早期の無菌化を目指す。
- 適応と禁忌(臨床判断ポイント)
- 選択的が適する場面:無症状の深在性う蝕、若年歯、露髄リスクが高いケース、確実なフォローが可能な患者。
- 選択的が不向きな場面:強い自発痛や持続的刺激痛・根尖病変がある場合、感染が既に広範な場合、フォロー不能な患者。
- 非選択的が適する場面:浅~中等度のう蝕、露髄リスクが低い場合、即時の感染除去が求められる場合。
- 実践プロトコール(概説)
- 選択的削合(一回法)
- 問診・冷温・電気的歯髄検査・X線(必要時CBCT)。
- ラバーダム装着、唾液・感染対策。
- 辺縁は健全歯質まで形成して辺縁封鎖を確保。
- 歯髄側はfirm/affected dentinを目標に残存させる(主観的触診で判断)。
- 必要時、消毒やライニング(Ca(OH)2、MTA等)を使用。
- 密閉性の高い修復(恒久修復または高品質暫間封鎖)を実施。
- 定期的な経過観察(1か月→3か月→6か月→1年など)。
- 非選択的削合
- 同様の評価後、感染象牙質を徹底除去し健全象牙質に到達→修復・フォローアップ。
- ステップワイズ(段階的)法
- 初回で深部を封鎖し、数か月後に再評価して完全除去する二段階アプローチ(歯髄温存をさらに重視する場合に有用)。
- 利点・欠点の比較(臨床的意義)
- 選択的の利点:歯髄保存率向上、切削量低減による強度保持、若年症例に有利。
- 選択的の欠点:封鎖不良やフォロー不足で二次う蝕のリスク、判定が臨床的に主観的。
- 非選択的の利点:即時的感染除去、修復の一貫性確保。
- 非選択的の欠点:露髄リスク増、将来的に根管治療へ移行する可能性と歯質欠損の拡大。
Authority(権威性)— エビデンスとガイドラインに基づく立場
- 最近のランダム化試験および系統的レビューは、無症候性の深在性う蝕において選択的削合(単回法または段階法)が非選択的削合に比して歯髄保存に有利であるとの報告が増加しています。主要な歯科学会やガイドライン(欧州など)も同様の方向性を示す場合が多く、当院の方針もこれらのエビデンスを踏まえています。
- ただし成功の鍵は「高品質な辺縁封鎖」と「経時的なモニタリング」であり、エビデンスは手技・材料・アフターケアによって結果が左右されることを示しています。
Trustworthiness(信頼性)— 患者への説明・同意・フォロー管理
- 患者説明(インフォームドコンセント)
- 治療方針(選択的 vs 完全)、期待される効果、リスク(残存細菌・二次感染の可能性、再治療の可能性)、必要なフォローアップ頻度を明確に説明し、患者の価値観・環境に合わせて共同決定します。
- フォローアップ指針
- 標準的観察:1か月→3か月→6か月→1年(症例により調整)。症状悪化やレントゲンでの根尖陰影出現があれば速やかに再評価・再治療(根管治療等)を行います。
- 実務上の留意点
- ラバーダム等の無菌操作、接着操作の厳密さ、適切なライニング材と修復材の選択が成功率を左右します。
- 初回治療の方針は将来の修復性や保存性に大きく影響するため、保存優先か完全除去優先かを臨床的に慎重に判断します。
(当院の立場)
- 東京国際歯科 六本木では、院長の豊富な経験と最新のエビデンスに基づき、個々の症例に最適なう蝕治療戦略(選択的削合・非選択的削合・ステップワイズ法)を提案します。患者様には利点・欠点とフォロー計画を丁寧に説明した上で、長期的な歯の保存を第一に考えた治療を行います。
主な参考文献(抜粋)
Fejerskov O, Kidd EAM (eds). Dental Caries: The Disease and Its Clinical Management.(教科書)― う蝕の病態生理と臨床的管理(外科的/非外科的治療の分類)を概説する標準的教科書。
European Society of Endodontology / Bjørndal L et al. Position statement on the management of deep caries and pulp exposures (2019) ― 深在性う蝕に対する選択的切削や保存的戦略のガイドライン的見解。
Fusayama T. Conceptual papers on infected vs affected dentin ― 感染歯質と影響歯質の概念を提示した古典的な文献(選択的切削の理論的根拠)。
系統的レビュー(例:Schwendicke F. et al.)― 部分的(選択的)う蝕除去と完全除去の臨床転帰を比較したメタ解析・系統的レビュー(う蝕除去量と歯髄保存,二次的アウトカムに関するエビデンス)。
Mjör IA, Gordan VV ほかの臨床疫学的研究 ― 修復物の失敗要因(二次う蝕、修復材料の劣化)と補綴の置換頻度についての報告(再治療による歯質喪失の累積を示唆)。
Ferracane JL, ほか接着修復に関するレビュー ― 修復材料特性と臨床寿命,辺縁封鎖の重要性に関する概説。
住所: 東京都港区六本木5丁目13−25 TIDSビル 2階
於多福坂沿い
電話番号: 03-5544-8544
最寄駅: 麻布十番駅 南北線・大江戸線 六本木駅 日比谷線
都営地下鉄大江戸線「麻布十番駅」7番出口より徒歩5分
クリニックまでの経路はこちらのビデオをご覧ください
- 東京メトロ南北線「麻布十番駅」4番・5番出口より徒歩5分
- 東京メトロ日比谷線「六本木駅」3番出口より徒歩10分
※東洋英和女学院中等部グラウンド裏手 お多福坂沿い
Tokyo International Dental Clinic Roppongi Information
Adress: 5-13-25-2 Floor, Roppongi, Minato-ku, Tokyo
Closest Station: Azabu Juban (Namboku Line / Oedo Line) Roppongi (Hibiya Line)
Phone Number: 03-5544-8544